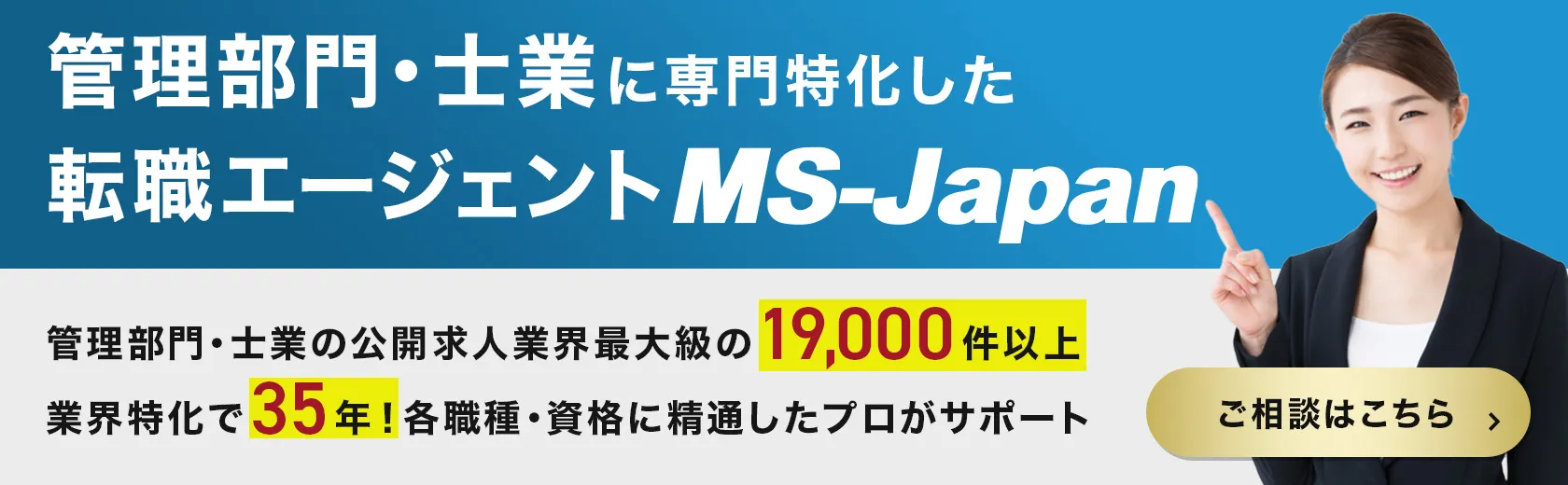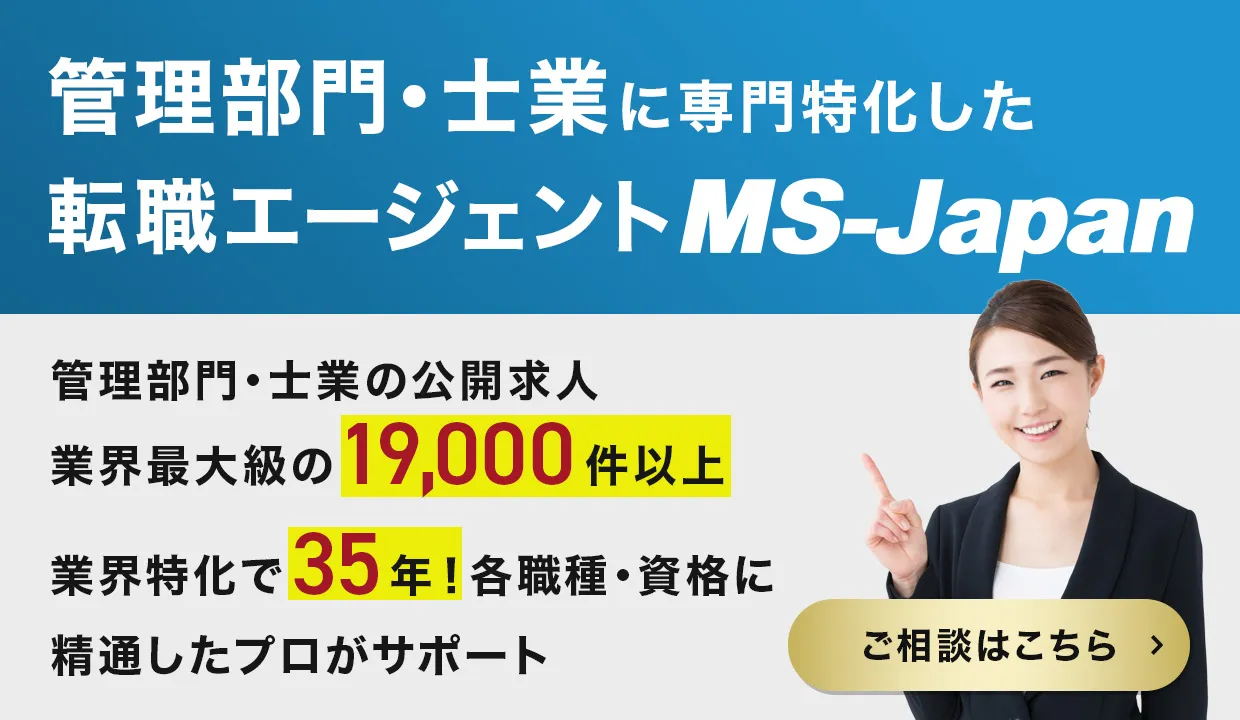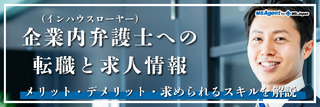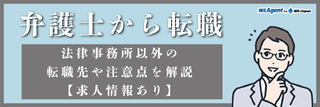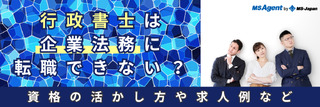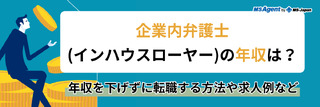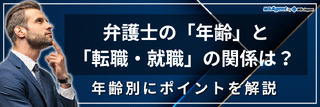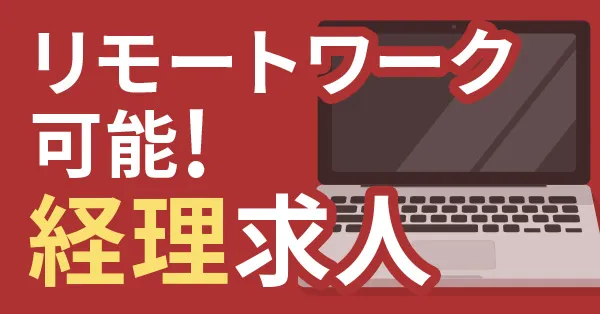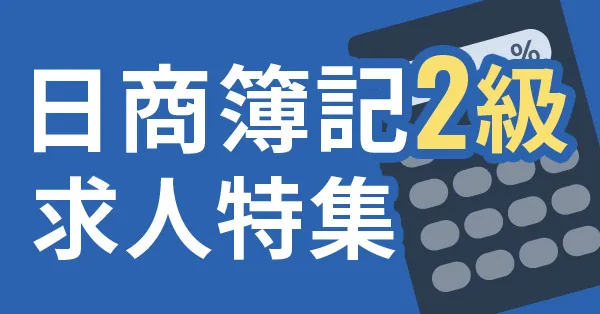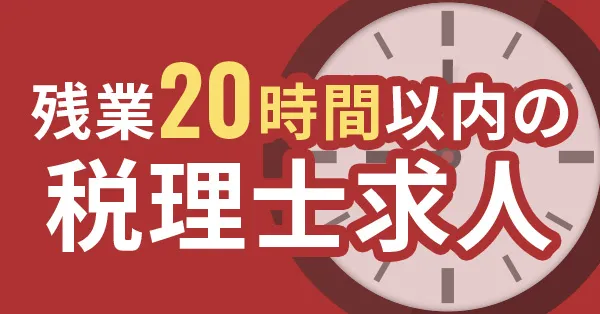弁護士の転職ならMS-Japan|弁護士の転職成功のポイントを徹底解説!

弁護士は法律分野における最難関の国家資格であり、活躍の場は年々拡大しています。
転職市場における採用ニーズが非常に多く、選択肢も多岐にわたるため、転職やキャリアの方向性に悩む方も多いでしょう。
本記事では、35年以上にわたり弁護士の転職支援を行ってきた管理部門・士業特化型転職エージェント「MS-Japan」が持つ弁護士の転職ノウハウを一部公開いたします。
弁護士の方から多く寄せられる疑問に答える内容を網羅していますので、転職活動中の方はもちろん、検討段階の方もぜひご活用ください。
※以下の記事の要約から気になるトピックを選んでいただくと、該当の章までジャンプできます。
弁護士の転職について
弁護士の最新転職市場は?
法律事務所への転職で押さえるべきポイントは?
一般企業への転職で押さえるべきポイントは?
弁護士の就職・転職に年齢は関係ある?
弁護士のキャリアパス・転職先について
【転職理由別】弁護士におすすめの転職先一覧
ワークライフバランスを整えたい弁護士向けの転職先
専門性を高めたい弁護士向けの転職先
年収を上げたい弁護士向けの転職先
人間関係の良好な職場で働きたい弁護士向けの転職先
弁護士の求人を確認する
弁護士の転職はMS-Japanにお任せください!
「MS-Japan」は、管理部門・士業に特化した転職エージェントサービスで、35年以上の豊富な業界知識・ノウハウや転職支援実績があります。
弁護士のキャリアに精通した”プロ”が転職をサポート!
「MS-Japan」には、専門分野ごとに分かれたキャリアアドバイザーが在籍しているため、弁護士の転職やキャリアについて精通したアドバイザーに相談することが可能です。
近年の転職市場は、情報収集が成功のカギを握る「情報戦」と言われています。
弁護士の転職についてノウハウを持つアドバイザーのサポートを受けることで、転職活動を有利に進めることができるでしょう。
弁護士の幅広いキャリアにあった求人を紹介!
「MS-Japan」では、法律事務所や企業内弁護士(インハウスローヤー)、コンサルティングファームなど、弁護士の多様なキャリアに対応した求人を取り扱っています。
また、35年以上の実績を誇る老舗エージェントとして、求人企業や法律事務所と強固な関係性を築いているため、ひまわり求人求職ナビや一般的な転職サイトには掲載されていない非公開求人もご紹介可能です。
管理部門・士業特化の転職エージェント「MS-Japan」では、業界に精通したキャリアアドバイザーがあなたの転職活動を全面的にお手伝いします。
弁護士の最新転職市場
まずは、弁護士の転職市場における最新の傾向を確認してみましょう。
一般企業を希望する弁護士が増加している
ここ数年は、一般企業への転職を希望する弁護士が増加しており、JILAによると2025年6月時点で3,596人が企業内弁護士として働いています。
これは、2020年のコロナ禍以降、リモートワークやフレックスタイムを導入する企業が増えたことが背景にあります。
法律事務所では、クライアント情報の管理や案件の進行体制の関係から、一般企業ほど柔軟な働き方を採用することが難しい場合が多いため、ワークライフバランスの改善を求める弁護士が一般企業へ転職する傾向が強まっています。
実際に「MS-Japan」にご相談いただく方も一般企業を希望する弁護士の割合が増加しており、企業内弁護士は弁護士のキャリアとして一般的なものになっているといえるでしょう。
参考:企業内弁護士数の推移|JILA
法律事務所では優秀な弁護士の取り合いに
一般企業に転職する弁護士が増えたことで、法律事務所では優秀な弁護士の獲得競争が激化しています。
そのため、大手・準大手や中堅の法律事務所でも、これまで以上に若手からベテランまで幅広い層を対象に採用を検討するようになっています。
また、企業のグローバル展開や、コーポレートガバナンス・コンプライアンスへの対応の重要性が高まったことで、一般企業での弁護士の需要も増加しています。
このように、法律事務所と企業の両方で弁護士の需要が高まっているため、弁護士にとっては売り手市場が続いており、転職を考えている方にとって有利な状況と言えるでしょう。
今後もこの活発な市場は継続すると見込まれています。
弁護士の転職が難しい?その理由は?
難関国家資格である弁護士資格であっても、「弁護士の転職は難しい」と言われることがあります。
その背景には、弁護士の転職市場やキャリアの多様化など、様々な要因が影響しています。
弁護士の増加による転職市場の激化
「弁護士の転職が難しい」と言われる理由の1つとして、2006年に導入された新司法試験制度の影響挙げられます。
司法試験制度の改革により、毎年1,500人程度だった司法試験合格者数が、2012年には2,102人まで増加しました。
しかし、弁護士が扱う事件の総数は大きく増えていないため、限られた案件を巡って弁護士同士での受注競争が起きています。
こうした状況が、弁護士の転職市場での競争をより厳しくし、スキルや経験に応じた年収格差も広がる傾向にあります。
また、採用側も「大きく貢献できる経験豊富な弁護士」を求めるため、特に若手や実務経験が少ない弁護士にとって、転職市場での競争は一層厳しいものとなっています。
AIやテクノロジーによる弁護士需要への影響
AIやリーガルテックツールの普及により、契約書レビューや法務リサーチなど、従来弁護士が行っていた業務を効率化するケースが増加しています。
そのため、弁護士には法律知識だけでなく、こうした変化に対応し、AI・リーガルテックに関する知識や他分野での実務スキルを積極的に身につけることが求められます。
あわせて読みたい
キャリアの多様化
弁護士のキャリアは、法律事務所だけにとどまらず、一般企業、コンサルティングファーム、任期付き公務員など、多岐にわたるようになりました。
また、法律事務所でも、企業法務や国際法務、知的財産といった専門分野の案件が増え、企業でも海外進出にまつわる法務やコンプライアンス業務など、弁護士の役割が多様化しています。
選択肢が広がった分、転職の成功が単純に新しい職場を得ることではなく、自分の目的やキャリアビジョンに合った転職先を見つけることに重きが置かれるようになりました。
このため、転職先選びの難易度が上がり、より慎重なキャリア設計が求められています。
弁護士の主な転職先
弁護士の代表的な勤務先としては「法律事務所」や「一般企業(インハウスローヤー)」が挙げられますが、「コンサルティングファーム」「任期付き公務員」も転職先の選択肢として考えられます。
それぞれの転職先について、詳しく解説していきます。
法律事務所
法律事務所は、大きく分けて一般民事系事務所と企業法務系事務所に分かれます。
一般民事系事務所
一般民事系事務所のメリットは、比較的ワークライフバランスが整っている事務所が多い点です。
これは、企業法務と比較して案件1件あたりの処理時間が短く、1人で担当するケースが多いため、個人のペースで業務調整をしやすいことが要因だと言えるでしょう。
また、一般民事系事務所では個人受任を容認するケースも多いため、事務所案件で収入を得ながら、独立に向けて自らのクライアント開拓を並行しやすいこともメリットです。
企業法務系事務所
企業法務系事務所の魅力は、報酬の高さと専門性の高さです。
大手事務所では、優秀な弁護士の場合、1年目でも年収1,000万円を超えるケースがあり、パートナークラスになると億単位の年収を得ることも可能です。
その分、案件が大きく、1件の処理に要する時間が多くなるため、激務となるケースが多いでしょう。
弁護士としての実務経験や、収入を重視する方にはおすすめの選択肢です。
ただし、企業法務系事務所は取り扱い分野や事務所の体制によって働き方が異なります。
大手事務所のように大型案件を複数人の弁護士で対応する事務所もあれば、ジェネラルコーポレート(一般企業法務)を中心として、単発の案件はそれほど多くない事務所もあります。
ジェネラルコーポレート(一般企業法務)を中心とする事務所では、通常時は残業がほとんど発生せず、単発の案件が発生した時期だけ忙しくなるケースもあるため、「企業法務をやりたいけれど、常に忙しいのは避けたい」と考える方にとって有力な転職先候補になるでしょう。
一般企業(インハウスローヤー)
弁護士が一般企業に転職する場合、法務部に配属となるケースがほとんどです。
主な業務としては、(社員からの)法律相談や契約法務、コンプライアンス対策、法令調査、労務・労働問題、知的財産関係などがあります。
一般企業で企業内弁護士として勤務するメリットとしては、就業環境の良さがあります。
法律事務所では業務委託契約で働くケースが多く、個人事業主としての契約形態が一般的です。
一方、一般企業の場合は、基本的に正社員として雇用されるため、労務管理が徹底されており、ワークライフバランスが整った働き方ができるでしょう。
また、福利厚生面に関しても法律事務所と比較して、一般企業のほうが充実しているケースが多いでしょう。
一般企業に転職する際に注意すべきは、「業務内容」「収入」です。
業務内容に関しては、様々なクライアント・案件に対応する法律事務所と異なり、基本的には自社の法務業務のみを行うため、ルーティン化された業務に面白味を見いだせない可能性があります。
また、管理職になると実務よりもメンバーや部下の管理業務の比重が増えるため、法律家としての実務が少なくなることもあります。
転職前に業務内容に関してはしっかりと確認しておくべきです。
収入面では、法律事務所から転職する場合は下がる可能性もありますが、勤務時間が短縮されるため、時間単価で考えればさほど気にならない範囲であることも多いでしょう。
収入とワークライフバランスのどちらを重視するのかは、転職前に自分の価値観をしっかりと考えておくことが重要です。
専門職採用等の特別枠で採用されるケースを除き、基本的には勤務先企業の給与規定・昇給規定に従います。
あわせて読みたい
外資系事務所
外資系の法律事務所は、高い報酬とグローバルな業務環境が特徴です。
1年目から1,000万円を超える年収を得られることも多く、特に若手弁護士にとって魅力的な報酬水準だと言えるでしょう。
海外企業や国内企業の国際案件が多いため、国際的な法務スキルを磨ける機会が豊富で、グローバルに活躍したい方に適した職場です。
ただし、所属している外資系法律事務所そのものが日本市場から撤退するリスクも伴うため、長期的なキャリアを考える際には、この点を考慮する必要があります。
また、日系法律事務所と比較して、外資系法律事務所のアソシエイト弁護士は、事務所内でのパートナー補助業務の割合が多く、クライアント対応が少ない傾向にあります。
そのため、パートナークラスでなければクライアントの開拓は難しく、将来の独立を目指す方にとっては、クライアントネットワークの構築に限界があると言えるでしょう。
あわせて読みたい
コンサルティングファーム
弁護士の業務経験や法律知識に加え、論理的思考力や情報収集能力はコンサルティングファームでも欠かせないスキルであるため、弁護士はコンサルティングファームからも高いニーズがあります。
また、昨今のコンサルティングファームではM&A案件が多いため、M&A案件の経験がある弁護士は転職市場で重宝され、幅広い選択肢から選ぶことができるでしょう。
法律事務所では、課題・問題がある程度具体化されてから依頼を受けるケースが一般的です。
しかし、コンサルティングファームでは、クライアントの新規事業の企画段階からタスクフォースに参加するケースもあるため、上流から事業・経営に深く関与できる点はコンサルティングファームならではの魅力とも言えるでしょう。
その他の選択肢として会計ファームやFAS
Big4などの大手の会計ファームでは弁護士も活躍しています。
弁護士として働く中で会計士や税理士などの他士業と協働したことがある方もいるでしょう。
大手会計ファームでは案件をワンストップで対応するため、弁護士を社内で採用するケースもあります。
M&A、企業再生、フォレンジックなど、会計ファームがよく取り扱う案件で弁護士の力が必要なケースも多く、弁護士のニーズは高いと言えるでしょう。
弁護士全体の中でも、会計ファームで勤務する弁護士は少数派であり、他の弁護士との差別化を図ることもできます。
任期付き公務員
弁護士の中には、任期付き公務員として官公庁などの国の機関で勤務する弁護士もいます。
金融庁や特許庁、公正取引委員会など選択肢は多岐にわたります。
その名の通り任期付きでの特別公務員となり、例外はありますが、基本的には3年程度の任期で公務員として勤務するケースが多いです。
任期付き公務員として勤務することで明確に自分の専門分野が確立されるため、キャリア形成におけるメリットもあります。
また、近年の円安や経済的事情により、海外留学が難しい弁護士も増えており、留学の代わりに任期付き公務員として勤務し、専門性を身につけるために、こういった選択をする人も少なくありません。
任期付きではありますが、ワークライフバランスが良く、報酬も安定しているため、選択肢の一つとして検討する価値があるでしょう。
あわせて読みたい
【転職理由別】弁護士におすすめの転職先
弁護士のよくある転職理由として、専門性、年収・待遇、ワークライフバランス、人間関係が挙げら
れます。
この章では、転職理由別におすすめの転職先をご紹介します。
専門性を高めたい弁護士におすすめの転職先
弁護士として専門性を高めたい場合は、「特定分野に専門性を持った法律事務所」がおすすめです。
すでに興味のある分野が明確な場合は、その分野に強いブティック系法律事務所を探しましょう。
また、現在の事務所から官公庁に出向する方法や、任期付き公務員として官公庁で勤務する方法もあります。
官公庁で法律・規則の立案作業や、行政実務など、普段の弁護士業務と異なる立場で仕事をすることで、弁護士業務とは異なる視点や特定法領域への理解を深められます。
中には、官公庁での業務経験を経て、その専門分野に強い事務所に転職する弁護士もいます。
さらに、一般企業への出向や転職も専門分野を持つために有効です。
出向・転職先の企業の業界・業種に関する法律分野の専門性を高めることができるだけでなく、依頼者の立場から企業法務に携わることで、ビジネスを企業の内側から理解できます。
そのため、再度法律事務所に転職したり、独立開業したりする場合にも、同業のクライアントに対して深い理解をもとにリーガルサービスを提供できます。
専門分野を持つための方法は様々あるため、自身の状況・志向にあった選択が重要です。
年収を上げたい弁護士におすすめの転職先
転職によって年収を上げたい場合は、法律事務所が一般的な選択肢となります。
※日本弁護士連合会『基礎的な統計情報(2023年)』を参考に作成。
弁護士の働き方として年収が高い勤務先は、法律事務所と言われています。
企業内弁護士として勤務する場合は、企業の給与テーブルに従うため、役員などになるケースを除いて、年収の上限が設定されますが、法律事務所であれば、場合によっては億単位の年収を得ることも可能です。
また、弁護士の収入源として「個人受任」による収入も重要です。
現在勤める事務所が個人受任不可である場合、個人受任ができる事務所に転職することで、年間に稼げる金額を上げることが可能です。
個人受任が可能な事務所は経費負担が3割程度であることが多いため、個人受任で年間300万円の売上があれば、約200万円の収入増が見込めます。
さらに、事務所によっては経費負担が1、2割ほどのケースや、まったくない場合もあるため、転職前に確認することが重要です。
優良な事務所に巡り合えれば、大幅な収入アップも期待できるでしょう。
ワークライフバランスを整えたい弁護士におすすめの転職先
弁護士がワークライフバランスを改善できる転職先は「一般企業」が代表的です。
弁護士は長時間労働になりやすく、若手のうちは体力もあり、経験を積むためにも多少の無理をすることも多いでしょう。
しかし、年齢を重ねたり、家庭を持ったりすることで、働き方を見直したいと考える弁護士が多い傾向にあります。
一般企業の場合、深夜や明け方まで及ぶような働き方はせずに、1日8時間程度の勤務時間が一般的です。
また、フレックスタイム制やリモートワークを導入している企業では、生活に合わせて柔軟に働くことができます。
一方、法律事務所の場合、事務所ごとに働き方は様々です。
法律事務所は忙しいというイメージがありますが、転職先によってはワークライフバランスを整えることは可能です。
一般的に、企業法務系事務所は忙しい傾向にありますが、一般民事系事務所や総合型事務所が有力な選択肢となるでしょう。
ただし、一般民事系事務所であっても忙しいケースや、企業法務系事務所であっても安定した働き方ができるケースもあるため、個々の事務所の運営方針を確認することが重要です。
人間関係の良好な職場で働きたい弁護士におすすめの転職先
人間関係の良好な職場への転職を目指す場合、事前の情報収集が重要です。
日本弁護士連合会の基礎的な統計情報(2024年)によると、実に97.8%の事務所が10名以下の人数で運営されています。
| 事務所規模 | 2024年 | 割合 |
|---|---|---|
| 1人 | 11,436 | 61.92% |
| 2人 | 3,176 | 17.20% |
| 3~5人 | 2,651 | 14.35% |
| 6~10人 | 808 | 4.37% |
| 11~20人 | 263 | 1.42% |
| 21~30人 | 63 | 0.34% |
| 31~50人 | 46 | 0.25% |
| 51~100人 | 13 | 0.07% |
| 101人以上 | 14 | 0.08% |
| 合計 | 18,470 | 100.0% |
小規模な事務所の場合、他の弁護士や事務員との人間関係はきわめて重要な要素です。
ボス弁や兄弁・姉弁、ベテランの事務員との関係性によって転職する弁護士も少なくありません。
転職先は一般企業でも法律事務所でも、人間関係の改善は期待できます。
ただし、同じ失敗を繰り返さないためには、転職エージェントなど第三者からの情報提供を受けたうえで、転職活動を進めるべきでしょう。
参考:基礎的な統計情報(2024年)|日本弁護士連合会
あわせて読みたい
法律事務所への転職を成功させる3つのポイント
弁護士の転職成功には「事前準備」が重要です。
ここでは、法律事務所への転職を成功させるための重要な3つのポイントを解説します。
転職の目的に合った法律事務所を選ぶ
法律事務所への転職といっても、自分がどのような業務をしたいのかによって選ぶべき事務所が異なります。
「弁護士の主な転職先」の章で解説しているとおり、事務所によって担当する業務の幅や取扱案件も異なります。
転職先を選ぶ際には、事務所の規模や業務内容が自身のキャリア目標と一致しているかをしっかり確認することが、転職成功の鍵となります。
好印象を与えるための面接対策
法律事務所への転職を成功させるには、面接などの選考対策も重要です。
特に経歴が浅い弁護士の場合は、アピールできる実績が少ないため、面接で今後の伸びしろややる気をしっかりと示す必要があります。
具体的には、転職理由や志望動機をポジティブに伝えることが重要です。
たとえ現職に不満がある場合も、ネガティブな表現は避け、「新しい挑戦ができる環境で成長したい」といった前向きな理由に言い換えましょう。
また、面接の場では論理的に話すことを心がけ、法律知識や判断力など弁護士としての資質をアピールすることも重要です。
あわせて読みたい
徹底した法律事務所の情報収集
応募する法律事務所について十分に情報収集しておくことが必要です。
業務内容以外にも、事務所の雰囲気や働きやすさを知ることができれば、求人選びに役立つだけでなく、面接での咄嗟の質問にも対応しやすくなります。
ただし、個人での情報収集には限界があり、事務所のホームページや募集要項だけでは、実際の雰囲気や働いている人の様子を把握するのは難しい場合もあります。
そのため、法律事務所の情報収集をより深く、より効率的に行いたい場合には、弁護士や法律事務所に精通した転職エージェントの活用も検討することをおすすめします。
法律事務所での弁護士の役職・ポジション
法律事務所への転職を考えている方は、法律事務所内での弁護士の役職・ポジションについても把握しておくと良いでしょう。
ここでは、法律事務所での弁護士の役職であるアソシエイト弁護士とパートナー弁護士、またパートナー弁護士以外のキャリアパスであるオブカウンセルとナレッジローヤーについて解説します。
アソシエイト弁護士
アソシエイト弁護士とは、パートナー弁護士の業務を補助する弁護士のことです。
アソシエイトとは「仲間」を意味する言葉であり、事務所経営には関与せず、パートナー弁護士と共に業務を担当する弁護士です。
アソシエイト弁護士を複数名抱える中堅以上の法律事務所は、案件の規模が大きいため、パートナー弁護士1、2名とアソシエイト弁護士2、3名程度でチームを組み、案件に取り組むことが多いです。
案件の規模や内容によっては、1チームが10名以上となるケースもあります。
アソシエイト弁護士は、パートナー弁護士の指導・監督のもと、案件の対応に必要な情報のリサーチや契約書等の書面のチェック・作成などを行います。
弁護士数が数十名以上の法律事務所では、「ジュニア・アソシエイト」と「シニア・アソシエイト」といった形で更に職位を分けるケースが多いです。
法律事務所によって異なりますが、おおむね弁護士経験5年ほどで「ジュニア・アソシエイト」から「シニア・アソシエイト」に昇格します。
パートナー弁護士
パートナー弁護士とは一般企業でいう役員に相当し、法律事務所の経営に関与している「経営弁護士」を指します。
法律事務所の場合は、パートナー弁護士が案件を獲得するケースがほとんどであるため、いわゆる営業も行う必要があります。
パートナー弁護士には、弁護士としての能力に加え、営業スキルや部下のマネジメントスキルなど、ビジネスマンとしての手腕も求められます。
また、パートナー弁護士は自分の事務所に出資していることが一般的であり、弁護士業務としての売上以外に、出資金額に応じて、事務所の利益配分を受けることができます。
ただし、法律事務所は必ずしもパートナー弁護士という役職を設ける必要はないため、経営に関与している弁護士をパートナーと呼称しない場合もあります。
そもそも、パートナー制度を取り入れていない法律事務所もあります。
上記の通り、パートナーは役職の名称であるため、「何名以上の法律事務所はパートナーが必要」などの決まりはありません。
傾向としては、数名の弁護士が所属する法律事務所でパートナー制度を導入するケースは少なく、単純にトップの弁護士を代表弁護士(ボス弁)、それ以外を所属弁護士と呼び分けることが多いです。
反対に、十数名以上の弁護士が所属する中規模以上の法律事務所では、パートナー制度を取り入れているケースが多い傾向にあります。
パートナーに昇格する年次は?
多くの法律事務所では、弁護士経験10年前後を目安にパートナーに昇格することが一般的です。
しかし、法律事務所によっては弁護士経験6~7年程度でパートナーに昇格するケースもあります。
比較的早い年次でパートナーに昇格できる事務所では、早期からクライアントとの直接のやり取りを経験できるため、スキルアップのスピードが速いというメリットがあります。
一方で、パートナーとして責任範囲が広がるため、それだけのプレッシャーがかかる点も留意が必要です。
また、すべてのパートナーが必ずしも事務所に出資しているわけではありません。
事務所によっては、昇格して間もないパートナーが「ノンエクイティ・パートナー」という出資を伴わない立場であるケースもあります。
この場合、出資を行い、事務所の経営にも関与しているパートナーを「エクイティ・パートナー」と呼ぶことが一般的です。
さらに、「ジュニア・パートナー」「シニア・パートナー」「マネージング・パートナー」の3段階に分かれている事務所も多く、ジュニア・パートナーとして経験を積み、シニア・パートナーに昇格し、その後さらに経験を深めてマネージング・パートナーに昇格する流れが一般的です。
このように、パートナー制度は事務所ごとに運用方法が異なります。
そのため、転職する際には、パートナー制度の有無、昇格までの年次の目安、パートナーに求められる責務などを確認することで、入所後のキャリアを具体的にイメージしやすくなるでしょう。
オブカウンセル
オブカウンセルの立場は、事務所によって異なります。
特別顧問のようなポジションを指す場合や、パートナーでもアソシエイトでもない所属弁護士を指す場合もあります。
後者の一例として、一流のスキルを持つが、時間的制約のある弁護士がいるケースが挙げられます。
他のパートナーと同水準の売り上げは難しく、昇格基準に満たないが、その人が退所すると事務所としては痛手になるというジレンマを抱えた場合、オブカウンセルというポジションに就任してもらい、双方にとって有益な関係を維持できるよう配慮をすることがあります。
この場合、業務上はパートナーの案件にアソシエイトと共にアサインされることが多く、パートナーとしてはチームにオブカウンセルがいることは非常に心強いでしょう。
ナレッジローヤー
ナレッジローヤーとは、事務所の知識管理を担当する弁護士を指します。
法律情報を整理し、アクセスしやすくすることで、事務所全体の効率を高める役割を担います。
また、新しい法律や規制の変更について、いち早く情報をキャッチアップし、事務所のスタッフを教育することも重要な役割です。
日本ではまだ普及途上のポジションですが、外資系法律事務所を中心に広がりつつあります。
法律事務所では、M&Aのスキームを構築など、法律以外のノウハウが必要なケースもありますが、過去事例が整備されていれば効率的に対応できるでしょう。
文書化されてこなかったノウハウを整理・蓄積し、法律事務所の「知識の番人」として存在するポジションが、ナレッジローヤーです。
【弁護士×法律事務所】の求人情報
アジア最大手の外資系法律事務所
| 仕事内容 |
|
アソシエイト~パートナー候補 ・M&A ・バンキング・ファイナンス ・証券/キャピタルマーケット ・プライベートエクイティファンド ・コーポレート/競争法 ・コンプライアンス ・クロスボーダー投資 ・事業再生/倒産 ・不動産 ・人事・労務 ・競争・貿易・各種規制 ・紛争解決と訴訟 、国際仲裁 など |
| 必要な経験・能力 |
| 弁護士 |
| 想定年収 |
| 800万円 ~ 2,000万円 |
医療分野に強みを持つ法律事務所
| 仕事内容 |
|
・医療事故事案処理 ・医療機関からの各種相談 ・損保会社からの各種紹介案件処理等 ※個人受任可 |
| 必要な経験・能力 |
|
・弁護士(70期以降を想定) ※インハウス経験のみの方もご応募下さい |
| 想定年収 |
| 650万円 ~ 750万円 |
法律事務所への転職成功事例
ブティック系法律事務所から五大法律事務所への転職した20代の事例
- Kさん(20代/男性)資格:弁護士
- 転職前:ブティック系法律事務所
- 転職後:国内大手法律事務所
Kさんは、ブティック系法律事務所で金融法務を担当していましたが、将来のキャリアを見据え、より幅広いスキルを身につけたいと考え、転職を決意しました。
年収を維持しながら新しい環境での成長を目指し、弊社にご相談いただきました。
転職活動では、経験を活かせる国内大手法律事務所のポジションに絞り、金融法務の専門性が評価されて順調に内定を獲得しました。
年収アップとスキルの幅を広げるという目標を達成しました。
総合型法律事務所からブティック系事務所へ転職した30代の事例
- Xさん(30代/男性)資格:弁護士
- 転職前:総合型法律事務所
- 転職後:ブティック系事務所
総合型法律事務所で一般民事から企業法務まで幅広く経験を積んできたXさん。
弁護士としてのキャリアを重ねる中で、専門領域を確立していきたいと考え、転職活動を開始しました。
Xさんは労働法を自分の専門分野にしたいという強い意志を持っていたため、労働法領域で著名な事務所をご紹介したところ、無事内定獲得となりました。
他にも法律事務所への転職成功事例は「弁護士の転職成功事例」をご確認ください。
一般企業(インハウスローヤー)への転職成功のポイント
一般企業(インハウスローヤー)への転職には、法律事務所とは異なる視点が求められます。
当事者意識が重要
インハウスローヤーとして企業で働く場合、法律事務所の弁護士が企業を見る視点とは異なり、企業の一員として経営方針や事業目標に貢献する姿勢が求められます。
単に法律相談を行うだけでなく、リスク管理やビジネスの成功に貢献する「当事者意識」を持って業務に取り組むことが重要です。企業の一員として主体的に関わる姿勢をアピールすることで、採用担当者からの評価を得やすくなるでしょう。
年収にこだわりすぎない
インハウスローヤーへの転職では、必ずしも法律事務所と同水準の年収が期待できるわけではありません。
一般的に、インハウスローヤーの年収は法律事務所の弁護士よりも低めであるケースが多いため、年収だけに固執せず、働きやすさやキャリアの幅を広げることに重点を置くことが重要です。
企業内での安定した働き方やキャリアの成長を視野に入れ、年収以外のメリットも考慮して転職先を選ぶことが成功のポイントです。
応募企業に合わせた履歴書・職務経歴書
インハウスローヤーへの転職では、応募書類の内容も企業向けに工夫が必要です。
企業の採用担当者は必ずしも法律の専門家ではないため、履歴書や職務経歴書は、簡潔かつ分かりやすい表現で自分の経験を伝えることが重要です。
特に職務経歴書では、応募企業の業務内容に関連する経験を中心に記載し、企業法務の経験を強調すると評価されやすくなります。
また、担当してきたクライアントの企業規模や業種に触れつつ、具体的な業務内容を明確に記載することで、応募先企業との親和性を効果的にアピールできます。
【弁護士×一般企業(インハウスローヤー)】の求人情報
平均残業20Hスタンダード上場の法務
| 仕事内容 |
|
・契約書作成 ・コーポレート法務 ・コンプライアンス対応 ・株主総会対応 ・リーガルリスクマネジメント ・戦略法務 ほか |
| 必要な経験・能力 |
|
弁護士資格 ※司法修習生や、一般民事経験のみの方も歓迎 |
| 想定年収 |
| 530万円 ~ 910万円 |
SaaS系スタートアップベンチャーの法務
| 仕事内容 |
|
・新規ビジネス立ち上げ支援 ・パートナーシップ締結の支援 ・投資家からの資金調達における法的観点での支援 ・契約書レビュー(業務委託契約・NDA等) ・コーポレートガバナンスの構築/運用 ・社内規程のドラフト/レビュー ・従業員向けのコンプライアンス教育 など |
| 必要な経験・能力 |
|
弁護士資格 ※以下いずれか必須 (法律事務所での法務経験・事業会社での法務経験) |
| 想定年収 |
| 1,000万円 ~ 1,200万円 |
一般企業(インハウスローヤー)への転職成功事例
一般民事系事務所から一般企業へ転職した20代の事例
- Fさん(20代/男性)資格:弁護士
- 転職前:中堅法律事務所
- 転職後:上場企業
Fさんは、中堅法律事務所で一般民事事件を担当していましたが、年収が著しく低く、生活も厳しくなる可能性あったことで、転職を決意しました。
企業法務は未経験のFさんは、企業内に同じ弁護士資格保有者がいること、教育体制が整っている大手企業という条件をメインに転職活動を進めました。
弊社からはFさんの人柄が上手く伝わるように、現場社員との面談が複数回ある企業を紹介しました。
その結果、経験豊富な他候補がいる中、Fさんの実直なお人柄、基礎能力の高さが評価され、希望条件を満たす上場企業で大幅な年収アップの転職を実現しました。
一般民事系事務所から一般企業へ転職した30代の事例
- Oさん(30代/男性)資格:弁護士
- 転職前:民事系法律事務所
- 転職後:業界大手メーカー
Oさんは、地方の民事系法律事務所で幅広い法律案件を経験していましたが、知見を広げるために首都圏でのインハウスローヤーを志望し、転職を決意しました。
当初、企業法務の経験不足が課題となりましたが、転職への情熱と事業理解への努力が評価され、業界大手メーカーから内定を獲得しました。
年収も120万円アップと大幅に増加し、新たな環境でのキャリアをスタートされています。
企業法務系事務所から一般企業へ転職した40代の事例
- Aさん(40代後半/男性)
- 転職前:企業法務系法律事務所(パートナー)
- 転職後:東証スタンダード上場企業
Aさんは、企業法務系法律事務所のパートナーとして幅広い業務に携わっていましたが、案件の波による仕事と収入の不安定さから、安定した環境を求めてインハウスローヤーへの転職を決意しました。
転職活動の末、安定した業績と手厚い福利厚生のある東証スタンダード上場企業でありながら、副業もできる企業に入社を決めました。
転職活動では、優先順位を明確にし、継続性と収入の安定を実現できる企業法務のポジションを見事に獲得されています。
他にも一般企業への転職成功事例は「弁護士の転職成功事例」をご確認ください。
20代~40代【年代別】弁護士の転職成功のポイント
法務省が発表した「令和6年司法試験の採点結果」によると、同年の司法試験合格者の平均年齢は26.9歳です。
弁護士登録には合格後1年間の司法修習が必要であることを考慮すると、資格取得は20代後半となるでしょう。
そのため、20代の転職では、実務経験の程度よりも、弁護士資格を保有していること自体が評価され、就職・転職で年齢がネックになることはまずありません。
法律事務所が採用を検討する場合も、年齢よりもポテンシャルを重視します。
ただし、ポテンシャルの定義は事務所によって異なり、司法試験の合格順位や学歴を基準にする事務所もあれば、コミュニケーション能力や向上心などを重視する事務所もあります。
30代は「実務経験」をアピール!
30代の場合は弁護士になった年齢によって、経験年数は様々ですが、同期の弁護士と比較されることが増えてきます。
30代前半であれば、即戦力となるレベルの経験・知識は必要は、必ずしもありませんが、30代後半になると、一般民事事務所から企業法務事務所への転職など、キャリアの路線を大きく変えるハードルは高くなるでしょう。
キャリアの方針を変更するのであれば、できるだけ30代の早いうちに自らの興味・関心のある分野を固めて、その方向でキャリア構築をしていくことがおすすめです。
あわせて読みたい
40代は「自分だけの強み」で差別化!
実務経験を重ねてきた40代の弁護士であれば、自らの経験を活かし、活躍できるフィールドを選ぶことは難しくないでしょう。
しかし、法律事務所は一般企業と異なり、内情や社風があまり世間に知られていないことも多々あります。
入社後に、「面接時に聞いていた話と違う」と感じてしまう事態を防ぐためには、転職エージェントなどの法律事務所に詳しい人に相談してみることがおすすめです。
一方で、40代から弁護士としてのキャリアをスタートした場合など、実務経験が比較的浅い場合はどうでしょうか。
弁護士としてアピールできる要素が少ないため、転職を成功させるには、経験以外の要素でもアピールする必要があります。
では、40代の弁護士は「新米」ではいけないのかというと、そのこと自体はまったく問題ありません。
40代で実務経験が少ない弁護士は、法学部から法科大学院へ進んだ弁護士にはない、別のフィールドでキャリアを積んできた強みやアピールポイントを伝えることが大切です。
あわせて読みたい
ここまでご紹介した通り、弁護士の転職では「何歳までにすべきか」という年齢制限はないと言えるでしょう。
近年は人手不足が深刻化し、転職市場全体で求職者が有利な「売り手市場」となっており、弁護士だけでなく、一般的な職業においてもミドル・シニア層の転職が増えています。
しかし、年齢が上がるに伴って保有知識、経験などを厳しく評価されるため、年齢に相応するスキルを身に着けましょう。
転職で年収アップを狙うには
弁護士が転職を考える際に、年収は重要な要素でしょう。
転職で年収を上げるには、条件の良い法律事務所や企業の求人を狙うことが重要です。
一般的に、大手や外資系の法律事務所は年収水準が高い傾向にあります。
また、大規模案件を扱うため、スキルが磨かれ、将来的な年収アップも期待できるでしょう。
転職活動では、自分の専門性を活かせる職場や待遇の良い勤務先を見つけるために、転職エージェントを活用して入念な企業研究を行うこともポイントです。
弁護士の転職におすすめの時期はある?
法律事務所の場合
法律事務所の転職市場は、時期や季節によって求人数が大きく増減することはありません。
取り扱う案件の増加や欠員の補充などを理由とした求人が多く、通年で求人を出しているか、欠員のタイミングだけ求人を出すケースがほとんどだと言えるでしょう。
また、法律事務所の弁護士は、クライアントを持ち、訴訟などの業務を扱うため、急に職場を離れるわけにはいきません。
転職予定時期の3〜4か月前から準備を進めるスケジュールが一般的です。
法律事務所の面接は、パートナークラスの弁護士が担当するケースが多いため、面接日程の調整にも時間がかかる可能性が高いことも考慮しておきましょう。
企業内弁護士(インハウスローヤー)の場合
企業内弁護士の転職市場は、3月から4月にかけて求人数が増える傾向はありますが、他の月と比較して大きな差はないと言えるでしょう。
そのため、企業内弁護士の転職においても、季節要因はあまり考慮しなくても良いと考えられます。
企業内弁護士の転職活動では、選考回数が複数回設けられることが多いため、一次面接から内定まで1か月前後を要する場合も少なくありません。
また、企業内弁護士が他の企業へ転職する場合、条件交渉や部署異動を提案され、引き止められるケースもあります。
これらの事情を考慮すると、企業内弁護士の場合も転職予定の時期から、3〜4か月前ぐらいから準備を進める必要があるでしょう。
いずれにしても、計画的に余裕を持って転職活動を行うことが重要です。
- ・転職に向けて求人を含む情報収集を行う期間
- ・書類選考や面接などの転職活動を行う期間
- ・今の職場で業務引き継ぎを行う期間
この3段階を適切に進めるためにも、焦らず丁寧に準備を進める必要があります。
あわせて読みたい
弁護士の転職に学歴は影響する?
学歴に関しては、基本的に大きな影響はありませんが、一部の法律事務所では評価ポイントとされています。
例えば、五大法律事務所のような大手法律事務所では、出身の大学やロースクールも少なからず選考要素になるでしょう。
また、人気の高い企業法務系事務所などでは、司法試験の受験回数や試験成績について事務所独自の選考基準を設けているケースもあります。
こういった情報は、事務所のホームページに記載されていないため、事務所の内情に詳しい転職エージェントを活用して、情報収集することが重要です。
あわせて読みたい
検察官から弁護士として転職することは可能?
年次によって求められる経験や資質は異なりますが、検察官が法律事務所に転職し、弁護士になることは十分に可能です。
元検察官の弁護士は「ヤメ検」と呼ばれています。
検察官が弁護士を目指す場合、以下のポイントをアピールすると良いでしょう。
紛争案件に強い
ヤメ検は元検察官として、検察の動きや裁判所の意向を熟知していることが一番の強みです。
検察官が不利になるような弁護活動も身をもって理解しているだけに、逆にさまざまな場面で有利な状況をつくり出しやすいでしょう。
元検察官として、検察の動きや裁判所の意向を熟知していることが1番の強みです。
検察官が不利になる弁護活動について身をもって理解しているため、さまざまな場面で有利な状況をつくり出しやすいでしょう。
また、訴訟のプロセスに精通している点もアピールポイントの1つです。
例えば、企業法務を中心に扱っている大手事務所では、訴訟経験が少ない弁護士も多い傾向にあります。
そういった事務所では、訴訟・紛争案件に慣れている元検察官のニーズは高いと言えるでしょう。
安心感、ポテンシャルの高さ
検察官は、司法試験の上位合格者が多いため、優秀さと希少性を兼ね備え、公的機関での経歴も含めて、クライアントからの信用を得やすいことも特徴です。
また、検察官が弁護士職務経験制度で法律事務所に出向する際、危機管理・不祥事対応案件に携わるケースが多く、フォレンジック・コンプライアンスに専門性を持つ事務所と検察官の業務は親和性が高いと言えるでしょう。
裁判官から弁護士として転職することは可能?
裁判官は、起案能力や法律知識など、非常に高い水準が求められるため、司法試験だけでなく、司法修習での成績も重視されます。
そのため、元裁判官のキャリアを持つ人材はポテンシャルがある人材と評価され、転職に成功する可能性は十分にあると言えるでしょう。
ただし、裁判官は評価が高い一方で、必ずしも転職がうまくいくとは限りません。
司法試験合格者の中で、裁判官になる割合は極めて少なく、その数は全体の数パーセントに過ぎません。
そのため、法律事務所側が元裁判官からの応募を想定しておらず、求人として顕在化しづらい傾向にあります。
裁判官が弁護士を目指す転職活動では、法曹業界に特化した転職エージェントの利用がおすすめです。
転職エージェントは法律事務所とのネットワークを持っており、その事務所の求める人材を理解しています。
裁判官出身者を応募対象としていない事務所でも、転職エージェントから事務所に提案することも可能です。
弁護士の転職におすすめの転職エージェントの選び方は?
弁護士が転職エージェントを選ぶ際のポイントを紹介します。
特化型エージェントか総合型エージェントか
弁護士業界に精通した「特化型エージェント」は、業界知識や専用の求人情報を提供するため、弁護士向けのサポートに優れています。
一方、業種を問わず幅広い求人を扱う「総合型エージェント」では、より多様な転職先を検討することが可能です。
弁護士向けの求人数が豊富か
取り扱う求人数が多いほど、希望に合う求人に出会えるチャンスが広がります。
特に弁護士に特化したエージェントでは、弁護士を対象とした求人が充実しているため、希望に合った求人を見つけやすくなるでしょう。
サポートの充実度とスカウト機能
転職活動に不安がある場合は、職務経歴書の作成サポートやキャリア相談会など、サポートの充実したエージェントを選びましょう。
また、スカウトサービスが利用できるエージェントでは、企業や事務所からの直接オファーも期待でき、効率的に転職活動を進められます。
あわせて読みたい
【弁護士×転職】のよくある質問
法律事務所で、個人受任をした場合の経費負担はどのくらいですか?
経費負担の割合は、事務所規模や考え方によって異なりますが、2~3割が一般的です。
面接では、経費負担の割合に加えて、設定された根拠も確認しましょう。
経費負担の割合が低い事務所は、個人受任を奨励するところが多く、割合が高い事務所は、事務所の案件に積極的に取り組んで欲しいと考えているケースが多い傾向にあります。
インハウスへの転向を考えていますが、業界による業務の違いがありますか?
企業内弁護士の業務を業界で比較すると、金融機関とその他の業界では差異があります。
金融機関では、法務部のみならず、フロントやミドルの部門に弁護士が在籍し、商品設計や審査部門、投資銀行部門などで活躍しています。
その他の業界では、ほとんどの企業内弁護士が法務部門に所属し、契約法務や訴訟、コンプライアンス業務等を取り扱っています。
また、事業内容に伴って日々扱う法律も異なります。
メーカーであれば下請法やPL法等がメインですが、サービス業等ではあまり目にすることはないでしょう。
司法試験に向けた勉強との親和性を考えれば、不動産や建設等は比較的理解しやすい分野と言えます。
司法試験の合格順位は、就職活動でどの程度影響するのでしょうか?
選考における司法試験の合格順位の選考上の影響度は、応募先事務所と企業によって異なります。
法律事務所では、複数の弁護士を比較検討して採用するため、司法試験の合格順位の影響は少なからずあります。
特に比較対象の候補者が多い、大手法律事務所や人気の法律事務所は、より合格順位が高いほど選考上で有利に働く可能性が高いです。
一方で企業の場合は、必ずしも複数の弁護士を比較検討するわけではないため、司法試験の合格順位よりも、語学力や人物面の相性などの要素を重視する傾向にあります。
まとめ
当記事では「MS-Japan」をご利用いただいた弁護士の方にご相談いただくことが多いトピックを中心にまとめました。
転職の悩みは人それぞれであり、自身の価値観や現状、将来設計に基づいたキャリアプランを考えることが重要です。
弁護士のように専門性の高い職業についている方は、転職活動時はもちろん、転職を本格的に考えていない時であっても、今後のキャリア形成についてしっかりと考えておく必要があります。
MS-Japanには弁護士の転職に精通したアドバイザーが在籍し、転職活動の悩みをしっかりと伺い、キャリアプランを一緒に考えています。
弁護士としてのキャリアや転職をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
- #弁護士転職
- #弁護士
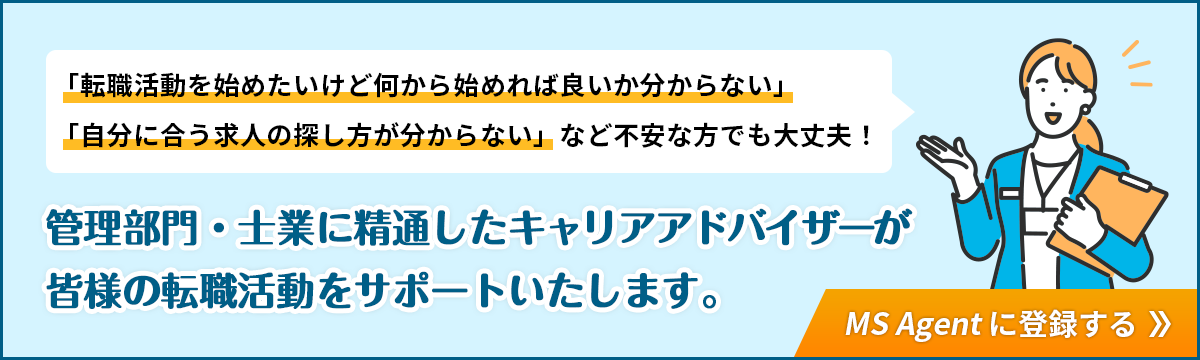
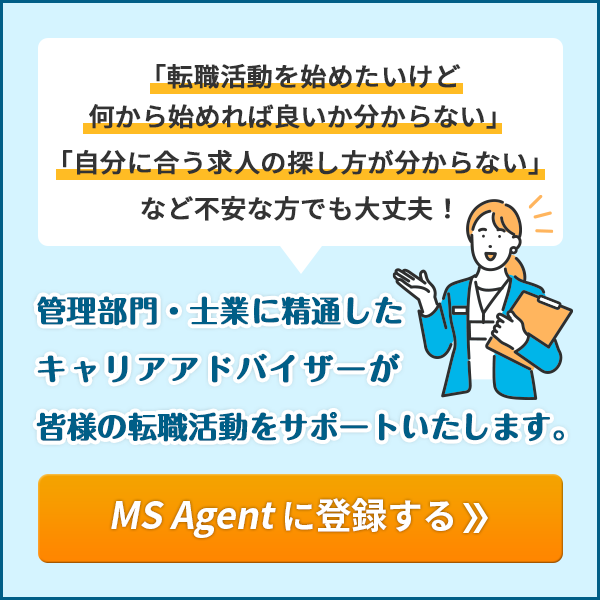
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、新卒でMS-Japanに入社。
法律事務所・会計事務所・監査法人・FAS系コンサルティングファーム等の士業領域において事務所側担当として採用支援に従事。その後、事務所側担当兼キャリアアドバイザーとして一気通貫で担当。
会計事務所・監査法人 ・ 法律・特許事務所 ・ コンサルティング ・ 金融 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 税理士科目合格 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

【2025年司法試験に強い大学ランキング】司法試験の合格率が高い法科大学院は?

会社法改正は法務人材のキャリアをどう変える?転職市場で評価される知識と経験(後編)

司法書士は就職・転職に有利?年代別ポイントや直近合格率など
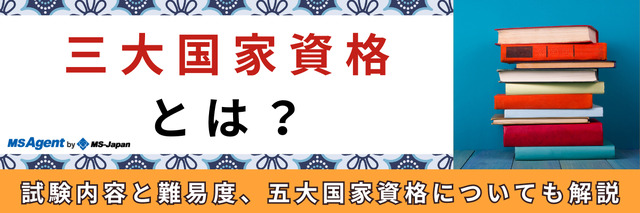
三大国家資格とは?試験内容と難易度、五大国家資格についても解説
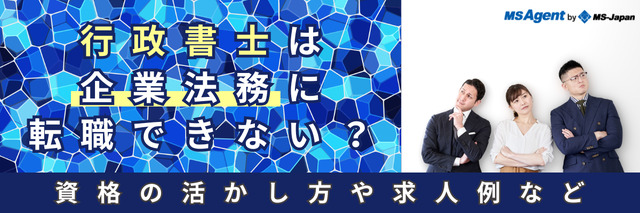
行政書士は企業法務に転職できない?資格の活かし方や求人例など
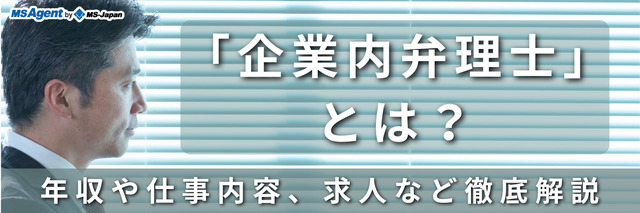
「企業内弁理士」とは?年収や仕事内容、求人など徹底解説
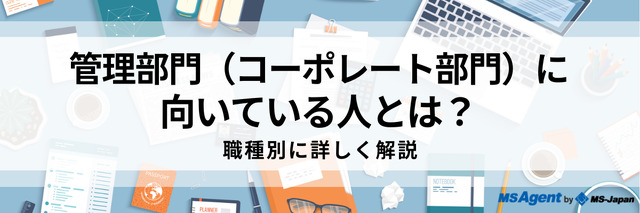
管理部門(コーポレート部門)に向いている人とは?職種別に詳しく解説

未経験でも転職はできる?MS-Japanの転職支援サービスを紹介!
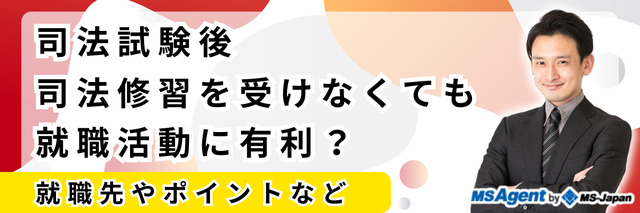
司法試験後、司法修習を受けなくても就職活動に有利?就職先やポイントなど